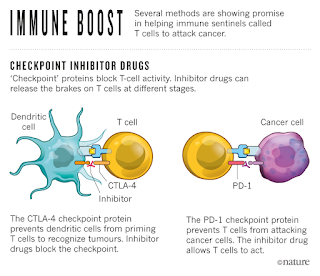厄介なリンジン;12/24、月曜日
昨日23日は、天皇誕生日で、けふは、苦しみ増すイブだといふ。 このタイミングで、またしても、・・・・・・ ジケンは20日に起こったとの報道あり。 http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-2921.html >> 岩屋防衛相は昨夜記者会見を行い、 ●国 海軍艦艇が20日午後、 海上自衛隊のP1哨戒機に 火器管制レーダーを照射 した事を明らかにしました。 レーダー照射は照準を合わせるロックオンと同じで、 「あとは引き金を引くだけ」の状態であり、 軍事行動、或いは攻撃予告ともいえる大変危険な行為。 たとえ照射された側が先に攻撃したとしても、 国際法上はまったく問題が生じないほどの事案で、 海上自衛隊幹部の話によると、 「よほどの緊急事態でなければ、現場だけの判断で照射しない」そうです。 >> 一方、アチラの反応はといふと; ●国 の海軍関係者はこの件に関して、 「遭難した北朝鮮籍の船の捜索の為艦艇の全てのレーダーを作動させたところ、 その範囲内に哨戒機がいるのを把握した」と説明 >> 銘記すべし、我が国防衛従事関係者の尋常ならざる忍耐力を。 石ころ以下の無法コッカでも、粛々と任務にあたっている。